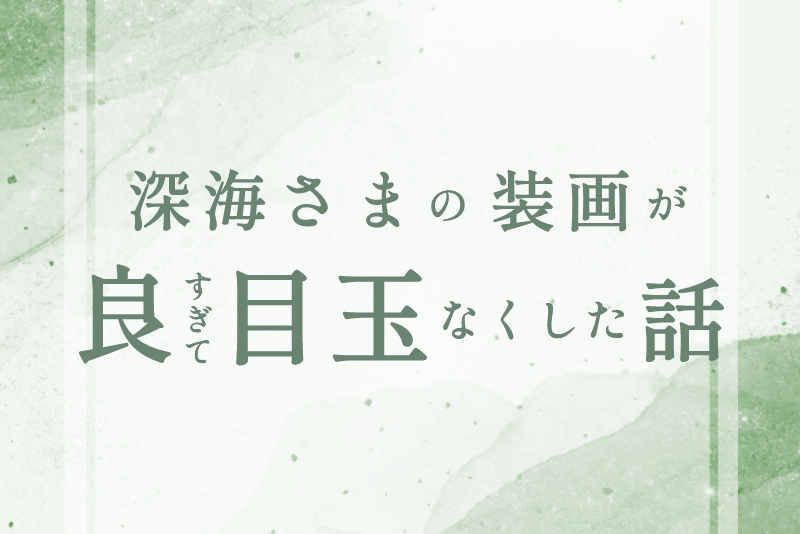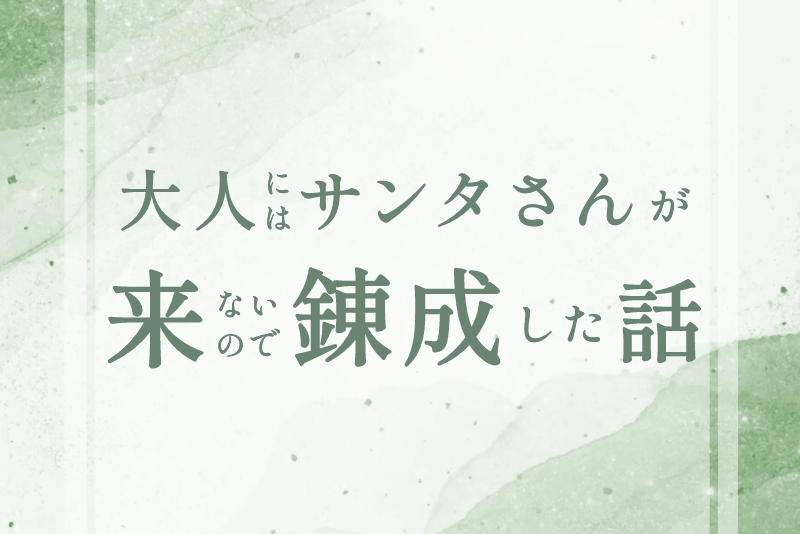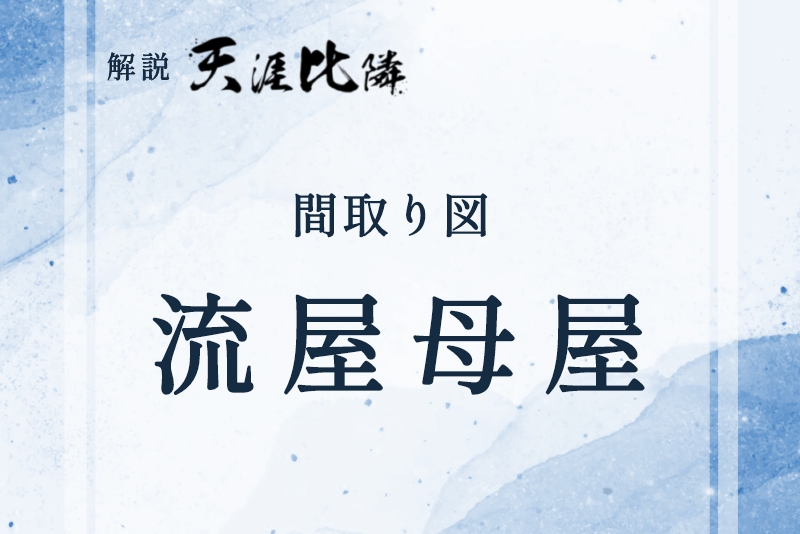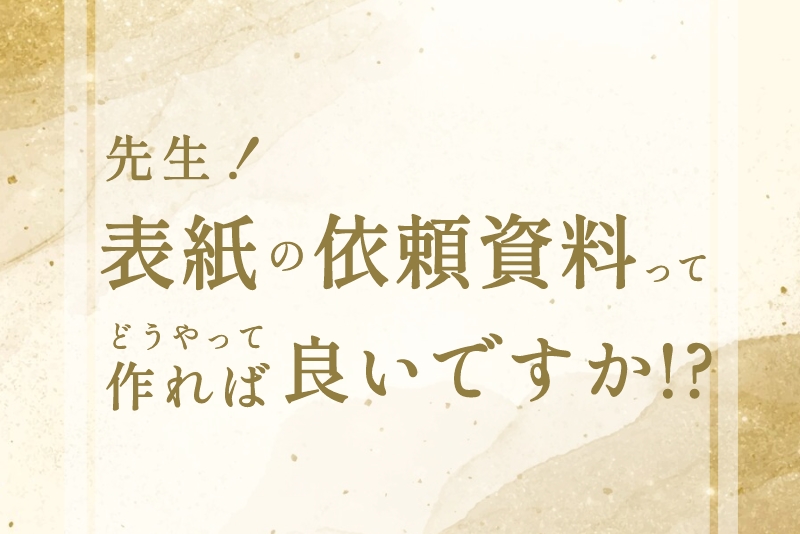MEMO
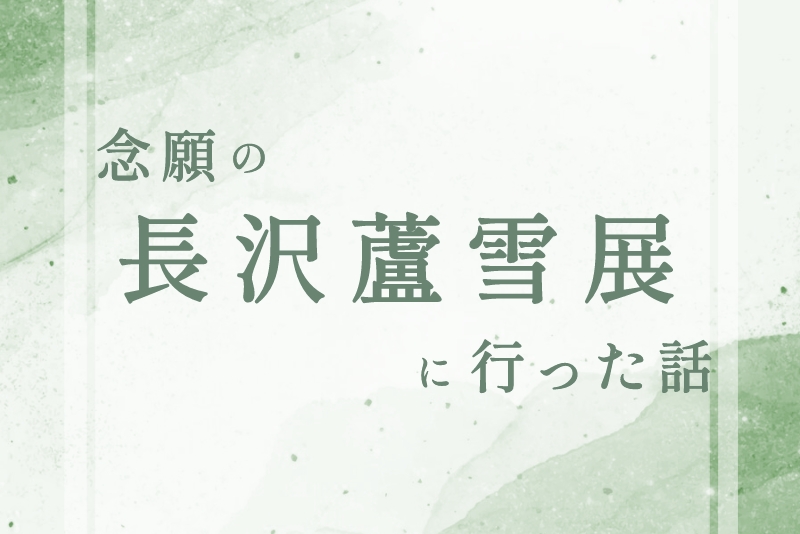
はしがき
諸事情で行けないとあきらめていた長沢蘆雪展に弾丸日程で行ってきました。
開催が明日(2024/3/31)までなので本当に滑り込み。
行けてよかった……。背中を押してくれた父母に感謝……。
以下からいつも通りの思考整理用だらだら日記です。
新鮮な覚書綴るの初めてなのでうきうきしてるし、文章がしっちゃかめっちゃかしてます。
長沢蘆雪という絵師
長沢蘆雪は、江戸中期に活躍した絵師。
けれど、その出生も若くして迎えた死も多くの謎を抱えたひとで、確定事項として分かっているのは、かの有名な円山応挙の高弟で、身分が下級武士だったということだけ。あとは残された多くの絵画たち。
そんな謎多き人物だからこそ、今でも人々の興味をひきつけてやまないのかもしれない。私もその一人。
好きを昇華させ5mmの行間5kmに広げて創作BLに混ぜこむぐらいの不遜レベルです、本当に申し訳ない……。
昨今はSNSの「蘆雪犬」バズりにより若い人の間でも名前が有名になりつつあるので、ちょっと嬉しいな~なんて思ったりしています。
今回の展覧会でもちらほら自分と同年代ぐらいの方(特に女性)がいらっしゃったり、親子連れの方々がいらしたり。絵画の鑑賞と同時に現在の鑑賞者層も把握できてとても面白かった。
今回の展覧会の監修者および琳派研究の第一人者である河野元昭先生曰く、「時代が奇想(蘆雪の画風)を求めている」影響もあるらしい。自由や自律、柔軟性を求めるこの令和の時代、確かに蘆雪の画風に合っているのかもしれない。
少し前までは辻惟雄先生の「奇想の系譜」で見出された一風変わった面白い絵師、ぐらいの認識だった。
それを境に美術史界でも再評価が進んでた感じでした。人の世の流れとは分からんものです。
ちなみに、その「奇想の系譜」で見出された絵師の中には伊藤若冲がいて、若冲の方が先に有名になっちゃった。なんか悔しい(?)。
蘆雪の絵は本当に「かわいい」だけなのか
昔の日本美術ってなんか小難しい……知識もないし見方もわからない……てなってる世間の印象を払拭するためか、最近はやたら「かわいい」をピックアップして紹介される江戸時代の日本美術。
特に蘆雪はそれが顕著で、「かわいい子犬を描く絵師」として師の円山応挙とともに紹介されがちです。
確かに「かわいい」は世間一般の共通認識として持てる感覚であり、鑑賞者の間口も広がる。一番取っ付きやすいラベリングなのかもしれない。
私は世間一般が「そうである」とすることに「本当にそうなん?」と意味なく考えることが好きな人間なので、「本当に蘆雪の絵は“かわいい”だけなのか」をメインのお題として、今回の展覧会の鑑賞に挑みました。
書けば長くなるのでめっちゃ簡潔に言うと、結論は「否」ではないかな~と。また「かわいい」ともてはやされているのは、「蘆雪が自身の感覚/世界を正しく鑑賞者に伝えるための工夫を惜しまなかった結果」なのではないかなと思いました(個人の感想)。
上手く伝わってるのかよく分からんが伝わって欲しい。
たとえば、子犬を始めとする動物画。雀、四十雀、幼子。蘆雪はそれらのほとんどをデフォルメ化して描いている。それにより、わかりやすく「かわいい」が誇張されている気がします。
蘆雪は写実主義の円山応挙の高弟であり、写実性には申し分ない技能があるし、それが滲み出ている作品も多く残されている。
虎図などは毛の1本1本を丁寧に細密に描き、ふわりとした毛並みを忠実に再現しているし、山水図においては狩野派の画技を学んだのかもしれない筆致も時折見え隠れしている。
なのに、動物画(特に小動物)となると意図的に筆致が変わる。世間一般で言う“蘆雪らしさ”が出てくる。
それは、蘆雪が特に「愛らしい」と感じていたモチーフだったからこそ、自身の感覚/世界が正しく伝わるよう敢えてかわいいが分かりやすくなるデフォルメ筆致で描いていたのではないか。結果として、我々鑑賞者に「かわいい」を想起させることに成功している……。
なんて頭のいい絵師なんだ……好きだが??(突然のオタク)
対比として、花鳥遊漁図巻や虞美人図では写実性を重んじた筆致が適用されていて、きちんと「美しい」という感情が先立つ。
色香や香り、光の加減、空気感を余すことなく伝えている。その時、「かわいい」という感情は凪いでいる。
つまるところ、現代風に言えばモチーフによって絵柄変えてるんですよ、この人……。
かと思えば、依頼人の「こういうところに飾る絵が欲しい」という要望があれば、依頼人の望んでいる感情が得られる筆致に極力合わせて作品を手がけている。ものすごい力量だと思います。
蘆雪は奇抜な構成の絵も多いので、変人で師に反発し自身の画技を鼻にかけた傲慢な性格だったのではとも言われているけど、依頼人の要望に合わせようとする姿勢や残された手紙の史料を見るに、至極真っ当な人で、相手のことも思いやれる、心に寄り添える優しい人柄だったのではないか。
今回、じっくり彼の絵を眺めてそんな風に思いました。
多くの筆致に対応できるよう、古画への研究やトレンドの収集、努力も惜しまない人だったのかもな、とも。
蘆雪は本当に絵を描くことが好きで、その絵でひとをあっと驚かせたり喜ばせることが好きだったのでしょう。
若い頃、「生涯、丹青三昧(絵を描くことに生涯を尽くす)」という言葉を度々口にしていた、との説もあるらしいので……。
今回の展覧会で、ますます長沢蘆雪という絵師が好きになりました。大阪で開催されてた方と前期展に行けなかったことだけが悔やまれます……!
今度は関東でもやって欲しい……!
おまけ小話
展覧会で見た作品のうち、構図が面白いなと思ったものの一つに『牛図』があります。
牛というモチーフに梅の描表装が施されていたのも相まって、太宰府で開催された本展にふさわしいともとれる非常に印象的なものだったというのもありますが、理由は他にもう一つ。
それは、鑑賞者をじっと見つめる牛のまんまるな瞳に、綺麗な藍色が使われていたことです。
江戸時代後期~幕末にかけて使われる藍といえば、やはり「ベロ藍」がすぐに浮かびます。
「ベロ藍」とは、葛飾北斎や歌川広重が愛した青とも言われる鮮やかな藍色で、彼らの手がけた作品にも多く使われた色です。ちまたでは「北斎ブルー」ないしは「広重ブルー」とも呼ばれています。
ゆえに、本作の牛と見つめ合っている折、「制作期が18世紀だし、使われているのはベロ藍かな? もしそうだとしたら、当時のトレンドを取り入れてるあたり勤勉だなぁ」なんて思っていましたが、図録の解説読むと「藍」としか説明されておらず……。
真相は闇の中……となっています。
真偽に関係なく、このようなことを自由に考えられる、また絵の前では自由に思考を泳がせられるこの瞬間が好きだからこそ、私は何度でも美術館に足を運んでしまうのかもしれません。
以上、長沢蘆雪展に行った感想でした! ここまでご覧頂きありがとうございます!
何かございましたら、お気軽にWaveboxまで!